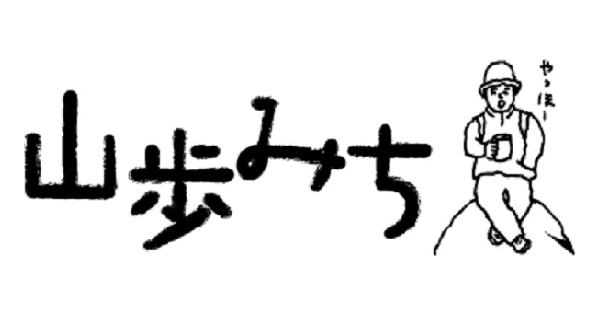フリーペーパー『山歩みち』2020年秋 036号掲載
※この記事はフリーペーパー『山歩みち』に掲載されたものに一部加筆、修正を加えたものです。基本的には取材時の内容となっておりますので予めご了承ください。
Profile
たなか・かんや 1965年生まれ。20代で数々の岩壁を登攀し、冬季初登は10ルート。90年から水平の冒険に移行し、カナダへは20年間通い続け、2万2000kmを踏破。2014年に第18回植村直己冒険賞を受賞した。
山の本当の姿に触れるために
――近年は毎冬、津軽の山に通っていますが、なぜ津軽に?
田中 まだ20代だったころ、同じ山岳会の先輩が「冬の東北の日本海側の山はハンパない」と話してたんです。その先輩は積雪期の黒部や剱岳、ヨーロッパアルプスやヒマラヤの壁も登ってて、そんな人が「ハンパない」って言うぐらいだから、相当すごいんだろうな、と。そのことがずっと頭に残っていて。それで40代半ばになって、「登ってみよう」と思い立ったんです。
――暴風雪になりそうな日にあえて登っているんですよね。
田中 ええ。昔、冬の登攀をやっていたころは、山のコンディションがいちばんいいときを狙って登ってたんです。困難なルートを登る場合、それはそれで合理的な判断なんですけど、あるとき「山の本当の姿に触れられてないんじゃないか」と感じてしまって。ルートの難しさを追求すればするほど、コンディションのいいときばかりを狙うから、山の本質からは離れてしまっているんじゃないか、と。
また、一般の人から「なんで、そんなことを?」と理解されなかったり、「危険だ」「無謀だ」と否定されてこそ、やる価値があるんじゃないかと思っていて。角幡(唯介)さん(※1)が「冒険とは、クライミングにおけるランナウト(※2)だ」とどこかで書いていたけど、まさにその通りだと思いますね。
――ブログを拝見すると、登山後の感想として「見たかった光景に出会えた」と書かれています。幹也さんの「見たかった光景」とは?
田中 冬山を登っている人ならきっと誰もが経験あると思うんだけど、連日吹雪で真っ白な世界に閉じこめられるなか、風が来て一瞬だけ視界が開け、稜線や山頂が望めることってあるじゃないですか。僕はわりとそんな瞬間が好きで。なんていうか、自分にとって冬山を登りはじめたころのイメージが、そうした光景なんです。
――過酷な自然の中に身を置くワケは?
田中 自然と対峙する中で「自分は今たしかに生きている」という手ごたえを得るため、かな。
――「日本初」「世界初」といった記録的な成果は求めていない?
田中 若いころは冬季初登とか意識してたし、カナダに通いはじめたときも、いかに踏破距離を延ばすかってことを考えていました。でも、ある時期から、結果に対するこだわりがなくなってきたというか。
たとえば、表向きの結果は「冬のカナダの長期縦走」となっていても、実質的には3月以降にほとんどの距離を稼いだりしていて、そうなると充実感に乏しかったりするんです。それより、距離的にはまったく進めなくても、厳冬期の過酷な環境下で試行錯誤しながらもがいていた方が緊張感があるし、自分としては面白いな、と。

――求めるものが変わっていく、きっかけがあったんですか?
田中 自分の感覚が変わりはじめたのは、40代の初めごろです。カナダでひどい凍傷を負って、帰国後に足指の先端を切断することになってしまって。その後、退院したときがちょうど新緑の季節で、久々に近くの山を登ったんです。そしたら、丹沢の簡単な沢をちょっと歩くだけでも、すごく満たされる感じがあって。それ以来、山で出会う美しい光景に目を奪われることも多くなりました。写真を整理すると、40歳ぐらいを境に日の出や夕日の写真がやたらと増えているんですよ(笑)。
――厳しい自然の中に身を置くことで、たしかに強烈な「生の実感」を得られたり、美しい光景に出たりするかもしれません。しかし、過酷さを求めつづけることは、死のリスクに近づいていく面もあるのではないでしょうか。
田中 そこはゲーム感覚というか。追いつめられたギリギリの状況の中で試行錯誤を繰り返し、いかに生還するかということが、自分にとってはひとつのゲームなんです。
もちろん死に対する不安や恐怖がないわけではありません。ただ、それは厳冬の津軽やカナダに限った話ではないんです。たとえば、丹沢の簡単な沢を登りに行くときも、図書館で借りている本とかは必ず返してから山に入ります。

――それは不測の事態に遭遇し、無事に山から下りられないことを想定して?
田中 そうです。そもそも自分は独りで入っているし、沢の中ってほぼ携帯電話はつながりません。しかもヘルメットもロープも持っていかないから、もしフリーソロで滝を登っているときに落ちたら、打ちどころが悪ければそのまま即死って可能性もあるし、ケガをして動けなくなればその場で野垂れ死にってこともあり得ます。まあ、だからこそ面白いとも言えるんですが。
冒険は前衛芸術に似ている
――先ほど「冒険は、一般の人から否定されてこそ、成り立つ」とおっしゃっていましたが、その言葉を裏返せば「大衆に認められたら、冒険は成り立たない」となります。実際、20年間にもおよぶ厳冬のカナダの旅に区切りをつけたのは、2014年の植村直己冒険賞(※3)の受賞がきっかけだったそうですね。
田中 自分がやってきたことを評価してもらって嬉しさもあったのですが、一方で植村直己冒険賞という有名な賞をもらうことに戸惑いもあり、複雑な気分でした。もしかすると厳冬のカナダに対するモチベーションが下がりはじめていたのかもしれませんが、冒険賞の受賞がひとつのきっかけなったことは事実です。
――他者や社会からの評価を求めないのであれば、極論かもしれませんが、記録を残さないという選択肢もあるんじゃないかと。幹也さんが若いころに傾倒したという立田實さん(※4)は、登山記録をほとんど残さず、わずかな山行ノートも自らの死の直前に焼き捨てています。幹也さんにとって「記録」とは?
田中 記録には2つの側面があると思っていて。ひとつは、その人のやってきたことを示す、言うなれば肩書きのようなもの。ひとかどの実績を作るにはやはりそれ相応のエネルギーが必要だし、その人の生き方や考え方を反映している面はあると思うんです。一方で、記録とはその人の過去であり、それに固執してしがみつくのは堕落しはじめている証拠というか。上手く言葉にできないんだけれど、その人の強さと弱さの両面を表している、矛盾したものが「記録」なんじゃないか、と。
じゃあ、なんで自分は記録を残すのかといえば、前衛芸術に置き換えるとわかりやすいかもしれません。とある芸術系の人から聞いた話ですが、前衛芸術って大衆に受け入れられてしまったら、もはや「前衛」じゃないけど、かといって誰からも相手にされないとそれはそれでダメなんだそうです。社会や大衆から完全に孤立するのではなく、一部の人からだけでも評価を得てこそ、前衛芸術として成り立つことができる。冒険もそれに近いのかな、と。
だから、冬のカナダに通いはじめたころ、自分の旅に関心を示す人が皆無だった中で、遠藤甲太(※5)に「いいですねぇ」と興味をもたれたのは、個人的にはかなり嬉しかったですね。彼とはその後、登山史年表の作成を一緒にやらせてもらったのですが、魅了される山や登攀の好みが似ていて、不思議と話が合いました。
何かをする意味は自分で決める
――お話を聞いていると、細貝栄さん(※6)の影響が大きいように感じます。
田中 高校生のときにはじめて『限りなき山行』と出会って、以来、何回も読み返してますね。この本の中で、自己や自然と闘って克服するような厳しい登攀も好きだけど、自然の美しさや安らぎを求めて彷徨う漂泊の山旅も好きだ、みたいなことが書かれているんです。そうした価値観、振れ幅の大きさがいいな、と。ただ、その感覚ってガチガチなクライマーには通じなかったりするんですけど。

――幹也さんにとってのカナダや津軽のように、全身全霊で打ち込める対象に出会うにはどうすれば?
田中 本や雑誌はよく読んでます。カナダでも、怪我なんかで動けないときは、向こうの図書館に通って、アウトドア関連の書籍や雑誌のバックナンバーを読み漁ってました。そうやっていろいろな記録に触れていると、ふと「やってみたい」とひらめくことがあるんです。要は直感です。直感って「ヤマ勘」みたいにとらえられるかもしれないけど、実際にはこれまでの経験によって培われた頭のなかの方程式に当てはめて、最良の方法を瞬時に判断したものなんじゃないかと考えていて。個人的には、直感にまさる判断はない、と思ってます。
もしまわりから「そんなことやって、何の意味があるの?」とか言われても関係はない。他者にとって意味がなくても、本人にとって意味があれば、それでいいんですよ。
――山に入り、自然と対峙するとき、心がけていることってありますか?
田中 まわりからの情報はシャットアウトしているかな。たとえば、最近の夏は立山の雷鳥沢にテントを張って、10泊とか長期滞在しているんです。山ヤにとって雷鳥沢なんて通り過ぎるだけの場所なのかもしれませんが、でも自分としては充実した時間を過ごせているんですよ。
さっきも話したように、本や雑誌で過去の記録を調べたりすることは徹底してやってます。でも、山に入ったら、読んだことはいったん忘れて、目の前に広がる自然や、自分自身の心や体の動きに集中します。読んだこと、聞いたことにとらわれちゃうと、現地の状況との間にギャップが生じてしまうかもしれないし、自分が本当に見たいものを見過ごしてしまうかもしれないなと思って。
――本誌読者のような初心者の場合、「これがしたい」と思っても、経験や知識が少ないので躊躇することもあるかと……。
田中 そうかもしれませんが、逆に初心者だからこそ、既成概念にとらわれず、思い切ったことができるんじゃないかな。振り返れば、自分のカナダの旅もそうでした。98年に山スキーでカナディアンロッキーを500キロ縦走したときも、実はそれ以前にスキーをしたこともなければ、冬のカナディアンロッキーを歩くことも初めてだったんです。そんなずぶの素人だから「無謀じゃないか」とも言われましたけど、知らなかったからこそできたんじゃないか、と。
それに、駆け出しのころって経験がないから、山に行くといろいろハマりまくるじゃないですか。でも、あとから振り返ると、そうしたハマった山行の方が思い出深かったりしません? 逆に経験を積んで、何でもスムーズにできるようになってしまうと、印象に残らないというか。
何かを知り、経験を積むことで、賢くなるのは事実です。でも、その反面、行動も思考も凝り固まり、大胆なことができなくなったりする。そう考えると、知らないこと、初心者であることって、かえってひとつの強みなんじゃないですかね。

取材日=2020年9月11日
《注》
※1|ノンフィクション作家であり、探検家。真っ暗闇の北極を彷徨った『極夜行』など、唯一無二な探検行を作品化し、数々の文学賞を受賞している。
※2|安全のためのプロテクションをほとんど取らずに登ること。
※3|植村直己の故郷・兵庫県豊岡市が主催する賞で、自然を舞台に冒険的かつ創造的な行為を成し遂げた個人または団体に贈呈される。
※4|国内外を渡り歩き、けたはずれの登山を行いながら、記録としてはほとんど残していないため、〝伝説化〟している登山家。その謎の生涯は、後述の遠藤甲太の『失われた記録-立田實の生涯』(『登山史の森へ』収録)に詳しい。
※5|冬の谷川岳一ノ倉沢などでの初登記録をもつクライマーであり、詩人・エッセイスト。『日本登山史年表』の編者であり、田中さんはその仕事を手伝っていた。
※6|田中さん曰く「登山家というより孤高の旅人」。彼の70年代の山行記録をまとめた『限りなき山行』(「あるくみるきく」147号)は知る人ぞ知る伝説的な冊子。
写真=中村英史、取材・文=谷山宏典